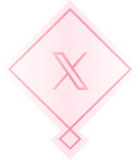最新情報INFOR
MATION
冬ビジュアル&ビジュアルイメージ動画<冬>解禁!原作・顎木あくみ書き下ろしSS公開!

原作・顎木あくみ書き下ろしショートストーリー
真っ白な花びらに似た雪片が、ちらちらと舞い始めたのは――とある曇りの日の午後のこと。
美世は灰色の雲に覆われ、日も差さず、緩やかに凍えていく寒空の下、早足で清霞の職場まで徒歩でやってきていた。
(よかった、本降りになる前に来られて)
片手で自分の傘を差し、もう片方の手には、清霞の傘を抱える。
自動車の急な故障により、運悪く今日に限って清霞は他の交通手段での通勤を余儀なくされたのだ。朝は晴れていたため、傘を持たずに。
「美世、悪かった。わざわざ」
屯所の守衛に事情を話してからすぐ、清霞が姿を現した。どうやら、帰り支度まで済んでいる。
「お仕事はよろしいのですか?」
「ああ」
清霞は白い息を吐きながら、美世の差し出した傘を受けとった。
二人は薄らと積もりだした雪の路を、しゃく、しゃくと音をさせて、寄り添い歩く。
美世がひとりで来たときは、あんなにも凍えそうで、どんより沈んでいた道のりが今は少し、暖かい。
「ありがとう、美世」
「いいえ。お役に立てて、よかったです」
帰ったら温かいお茶を出しますね、と美世が微笑むと、清霞もまた柔らかく口許を綻ばせた。